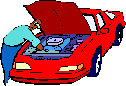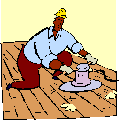ホーム > 組織でさがす > 県土整備部 > 道路課 > アセットマネジメントとは
関連分野
- しごと
- 道路行政
更新日付:2012年3月7日 道路課
アセットマネジメントとは
アセットマネジメントとは?
-
その名の通り(アセット=資産、マネジメント=管理・運用)、資産を効率よく管理・運用する、という意味があり、「アセットマネジメントシステム」はそのためのコンピュータシステムです。従来から、個人や企業の不動産・金融などの資産管理に用いられてきましたが、最近では公共の資産である社会資本にもこのシステムを適用しようという動きがあり、欧米諸国ではすでに多くの国がアセットマネジメントシステムの導入を進めています。
わが国でもアセットマネジメント導入の動きが広がりつつあり、平成15年4月、道路構造物の今後の管理・更新等のあり方に関する検討委員会(委員長:岡村甫高知工科大学学長)から発表された提言の第一項目に「アセットマネジメント導入による総合的なマネジメントシステムの構築」と題して、以下のように述べられています。
『道路を資産としてとらえ、道路構造物の状態を客観的に把握・評価し、中長期的な資産の状態を予測するとともに、予算的制約の下で、いつどのような対策をどこに行うのが最適であるかを決定できる総合的なマネジメントシステムの構築が必要である。』
もっと身近な例で説明すると・・・
-
私たちにとってもっと身近な資産である車や家を例にとって考えてみましょう。
車の場合、すり減ったタイヤを交換したり、古くなったエンジンオイルを入れ替える等の日常的なメンテナンスが必要です。また、安全に走行できるかどうかを確認するために車検という定期的な点検が義務付けられていて、車のどの部分が傷んでいるか、どの部品がどの位長持ちしそうか、といったことが分かりますので、いつ頃買い替えるのが最適かという判断ができます。
家の場合も、外壁の塗り替えや屋根の修理等の手入れから、部屋のレイアウト変更など、快適に住むために、そして長持ちさせるためにメンテナンスが必要です。
一台の車や一軒の家の場合、普段からこまめなメンテナンスをやっていれば、いつどこにどんな対策をするのが最適か、という設問に対する答えを求めることはそんなに難しいことではありません。
しかし、車の数が数百台、数千台になった場合、どの車のどの部品をいつ交換するのが最適か、という設問に答えるのは容易ではありません。また、車の種類や用途がたくさんあると、対策の優先順位をつけるためにその利用度合いや重要性を評価する必要も出てきますし、客観的な説明ができるように客観的な判断基準が必要となってきます。
対象となる資産の数が少ない場合は、人間の経験に基づいた判断で十分ですが、資産の数が多くなると対策の選択肢が急激に増えできますので、人間の経験だけで最適解を得るのは大変難しくなってくるのです。
道路橋の場合はどうでしょうか?
-
道路橋の場合も、基本的な考え方は車や家と大きな違いはありません。
下の図で道路橋のアセットマネジメント導入効果のイメージを簡単に説明します。
ケース1は、50年で架け替えをします。
ケース2は、延命かのための補修を順次行っていき、70年目には大規模な補修を行い、最終的に100年までの長寿命化を図ります。
その結果、橋の寿命を100年まで延ばすケース2の方がライフサイクルコストの縮減を図ることができたというイメージです。
ただし、車や家の場合は買い替えるのに大きな不便は生じません(車は移動できますし、家の場合も簡単に引っ越せます)が、道路橋の場合は移動することができないので、架け替えるとなると交通規制による不便を我慢してもらうか、あるいは仮橋を作って交通規制をなくす等の対策が必要になってきます。
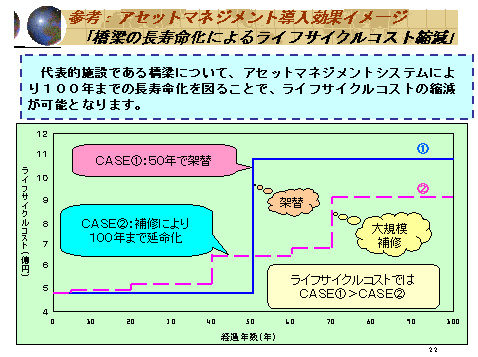
IT(情報技術)を活用します
-
アセットマネジメントシステムの構築が急速に広がろうとしている背景には、IT(情報技術)の急速な発展があります。
ITの活用によって膨大なデータの蓄積や解析が可能となったことから、道路橋の点検データの蓄積、劣化の将来予測解析、維持管理LCCの算定、重要度や優先順位の評価など、定量的かつ客観的な評価が可能になってきたことが、アセットマネジメントシステム構築の大きな引き金になっているのです。
維持管理の新しい潮流
- 道路構造物をはじめとする社会資本は、私たちの日常生活だけでなく経済活動を支える基盤です。今まで作ってきた貴重な社会資本を健全な状態で未来に引き継ぐことは、私たちの使命です。それは、豊かな自然や環境を未来に引き継ぐことと同じくらい重要な使命です。ITを駆使したアセットマネジメントシステムは、維持管理の新しい潮流です。