ホーム > 組織でさがす > 交通・地域社会部 > 地域生活文化課 > 青森県史叢書「馬淵川流域の民俗」
関連分野
- くらし
- 県外の方
- 青森県史
更新日付:2008年7月10日 地域生活文化課
青森県史叢書「馬淵川流域の民俗」
本書の概要
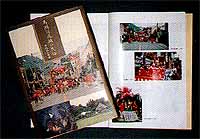
民俗の記録は、庶民の生活文化全般に及ぶ必要がありますが、本書では、社会構成・生業・衣食住・人生儀礼・年中行事・信仰・民俗芸能・口承文芸と八分野に分けて記述しています。このような民俗の分け方は、民俗学が従来採用してきた基本的な分け方ですが、本書においてもこれを継承したのは、青森県域を対象とするこれからの民俗研究にも資することを意図したからです。
この他に付録として、『大銀杏』という冊子を復刻し掲載しました。これは、昭和21~22年にかけて、名川町の現剣吉小学校、同中学校の教職員たちが中心になって、郷土の「常民の文化」を研究し発表したガリ切りの冊子で、現在では確認が難しい民俗も報告されています。



